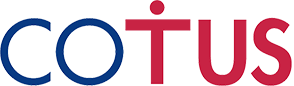スマホ・ゲーム依存と学習への影響 ― ご家庭でできる対策とは

スマホ・ゲーム依存と学習への影響 ― ご家庭でできる対策とは
目次
スマホ・ゲームと子どもの「学習意欲のジレンマ」ってなに?
近年、スマートフォンやゲーム機器の急速な普及により、子どもたちの生活環境は大きく変化しました。SNS、動画配信サービス、オンラインゲームといった刺激的で魅力的なコンテンツが身近にある一方で、「家ではついスマホを触ってしまって、なかなか勉強に取りかかれない」「夜遅くまでゲームをしてしまい、朝起きられない」といった声が、塾でも多く聞かれるようになっています。
スマホやゲームそのものが悪いわけではありません。しかし、使い方を誤ると、子どもの学習習慣や生活リズムに大きな悪影響を与えてしまうことがあります。特に思春期の子どもたちは、自制心や自己管理能力がまだ未熟であるため、自分一人でスマホやゲームの誘惑を断つのは容易ではありません。そこで今、保護者や教育者が子どもをどうサポートし、健全な学びの環境を整えていくかが大きな課題となっています。
スマホ・ゲーム依存が引き起こす3つの学習的悪影響ってなに?
スマホやゲームの長時間使用が、子どもの学習にどのような影響を与えるのか。塾の現場や家庭で見られる、主な3つの影響を以下にご紹介します。
① 集中力の低下
スマホやゲームは、短時間で強い刺激や快感を得られる設計になっています。これに慣れてしまうと、読書や問題集といった「静かで地道な活動」に取り組む際に集中力が続かなくなります。机には向かっているのに頭に入らない、気がつけば通知を見てしまう――このような状態では、学習の質は大きく下がってしまいます。
② 学習時間の減少
家庭での学習時間が、スマホやゲームの使用に取って代わられているケースも多く見られます。とくに受験を控えた時期は、一日一日の積み重ねが大切になるため、1〜2時間のロスも大きな差を生みます。「気づけば1時間ゲームをしていた」「少しだけのつもりが深夜になってしまった」といったケースが続くと、学力の定着にも支障をきたします。
③ 睡眠の質の低下
夜遅くまでスマホを操作することで、体内時計が乱れ、十分な睡眠が取れなくなる子もいます。光刺激により寝つきが悪くなり、朝の目覚めが悪くなるという悪循環もよく見られます。これは学習だけでなく、体調や精神状態、さらには成長期の発達そのものにも悪影響を及ぼす深刻な問題です。
ご家庭でできる!4つの対策と心構えってなに?
スマホやゲームへの依存を防ぎ、学習習慣を整えるためには、単に「やめさせる」のではなく、家庭の中での環境づくりと親の関わり方がとても重要です。以下の4つの対策を通じて、できるところから実践してみましょう。
① ルールの共有と一貫性
まずは家庭内でスマホ・ゲームの使用に関するルールを明確に決めましょう。たとえば「平日は1日1時間まで」「就寝の1時間前には使用を終了する」など、具体的で守りやすいルールがおすすめです。この際、子どもと一緒にルールを考えることが大切です。納得のいくルールを親子で共有することで、自主的に守る意識が生まれやすくなります。
② 学習環境の整備
集中できる学習環境を家庭内で整える工夫も効果的です。勉強時間中はスマホを別室に置く、通知を切る、アプリによって使用制限をかけるなど、物理的な誘惑を減らす対策を取りましょう。タイマー学習法(ポモドーロ・テクニック)を使ったり、塾の自習スペースなどスマホの誘惑が少ない場所を活用したりするのも有効です。
③ スマホ・ゲームに代わる楽しみを用意する
スマホやゲームへの依存は、他に楽しみを感じられる時間が少ないことが原因となっていることもあります。家族との会話、自然とのふれあい、スポーツ、読書、ボードゲーム、習い事など、「楽しくて、かつ健全な時間の過ごし方」を提案し、日常に取り入れてみましょう。親子で「スマホを使わない時間」をあえて設けるのも効果的です。
④ 親の姿勢が子どもに与える影響
子どもたちは大人の行動をよく観察しています。保護者自身が食事中もスマホを触っていたり、何かと画面を見ていたりすると、子どもにとってそれが「当たり前の姿」になってしまいます。まずは大人が手本を示すこと。家庭全体でスマホとの付き合い方を見直し、「適切な使い方」ができる文化をつくることが、長期的に見て最も効果的です。
塾と家庭が連携し、子どもの自律を支えるために
スマホやゲームは、今後ますます私たちの生活に欠かせない存在になっていくでしょう。だからこそ、「どう使うか」「どう付き合うか」がますます問われる時代となっています。学習意欲はあるのに、スマホやゲームの誘惑に負けてしまう――そんな悩みを抱える子どもは少なくありません。
塾では日々の学習の様子を観察しながら、必要に応じて保護者の方へのフィードバックやご相談も行っています。家庭と塾が連携して、子ども一人ひとりにとって最適な学びの環境を整えていくことが、将来の自律的な学習姿勢にもつながります。
スマホやゲームを「敵」とするのではなく、上手に付き合う力を育てること。それが、これからの時代を生きる子どもたちにとって、最も大切な力の一つではないでしょうか。
【無料体験はこちら】https://cotus.jp/entry/