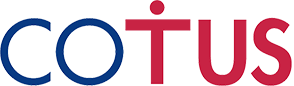岐阜全県模試?岐阜模試?岐阜新聞学力テスト? ― 中3受験生が受けるべき模試って、結局どれがいいの?
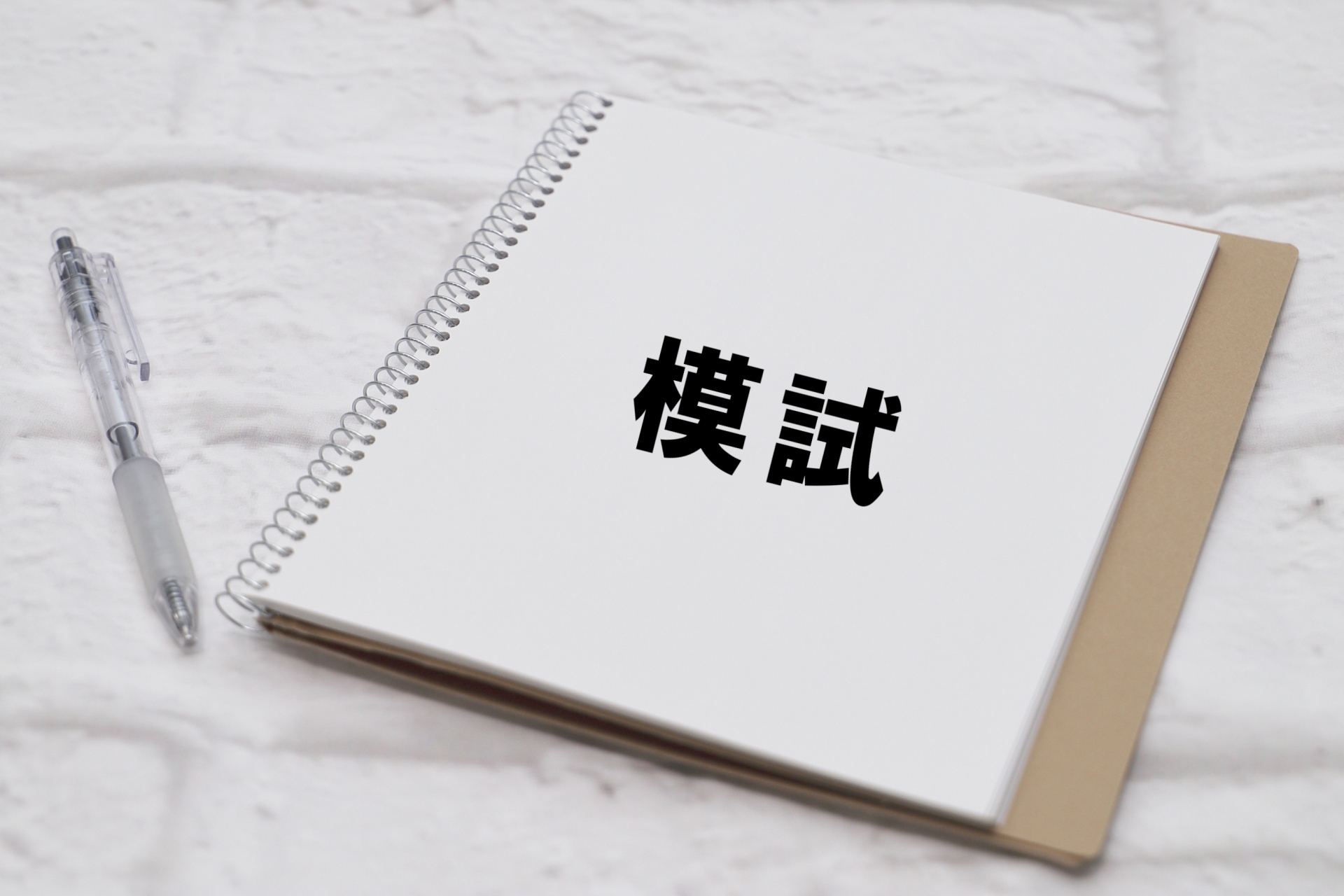
岐阜全県模試?岐阜模試?岐阜新聞学力テスト? ― 中3受験生が受けるべき模試って、結局どれがいいの?
受験が近づく中で保護者として気になるのは、「この模試、うちの子にとって本当に役立つの?」ということです。岐阜にはいくつか主要な模試があり、それぞれ特徴や難易度、使いどころが異なります。この記事では、岐阜新聞・中学3年学力テスト、志門塾の「岐阜模試」、学悠出版の「岐阜全県模試」を、回数・出題形式・偏差値の目安・判定の信頼性の観点から比較します。最後には、実際にどの模試を組み合わせて受けると効果的かについても具体的にお伝えします。
受験勉強について詳しくまとめた記事が2つございます。是非こちらもご覧下さい。
受験勉強っていつから何からする?おすすめの始める時期や勉強の仕方を個別指導塾が解説!
「先生、これから受験までに何をしたら良いですか?」~12月からの高校受験勉強の仕方を解説!~
目次
1. 岐阜全県模試(学悠出版)の特徴ってなに?
1-1. 出題形式・回数・実施時期
「岐阜全県模試」は学悠出版が企画する模試で、岐阜県の入試形式に沿った良問を揃えている点が売りです。実施時期は年度によって変わりますが、2025年度は第1回が8月、第2回が9月末~10月、第3回が12月~1月の期間で行われる形になっており、塾を窓口に申し込んで受験する仕組みです。成績資料や偏差値、内申とのクロス判定などが提供されます。2025年現在、岐阜県でもっとも受験者数が多い模試となっているのが、特筆すべき点です。
1-2. 難易度・偏差値・判定制度
岐阜全県模試は本番に近い問題構成で、問題難易度は標準的、本番よりもやや難しい作りとなっています。結果返却では、得点と内申点のクロス判定により志望校の合格可能性を示します。母集団が塾参加者を中心に広く集まるため、偏差値や判定の安定性は高いとされています。受験後の成績票は進路相談に使いやすく、塾の学習指導と合わせて活用されることが多いです。
1-3. メリット・注意点
メリットは、入試形式に沿った良問と、塾で手続きから成績受け取りまで完結できる利便性です。受験料は1回あたりの目安が公開されているおり、費用面の確認は事前に行う必要があります。実施回数や会場は年度ごとに変動するため、受験を検討する際は直近の案内で確認してください。また、全ての模試の中で最も母集団が多いため、偏差値算出や合格判定の精度が高い点は、最も大きなメリットになるでしょう。
岐阜全県模試への申込方法やもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい!
2. 岐阜新聞・中学3年学力テストの特徴ってなに?
2-1. 出題形式・回数・実施時期
岐阜新聞が運営する「中学3年学力テスト」は、公立入試に近い出題形式を意識して作られています。実施回数は年によって変わりますが、直近のスケジュールは年間で複数回(2025年度は9月から1月にかけて5回実施)となっており、公開会場での受験が可能です。例年、県内各地からまとまった人数が参加するのが一般的です。受験後は志望校ごとの合格可能性などを含む成績表が返却されます。
2-2. 難易度・偏差値・判定制度
岐阜新聞の学力テストは、県内の学力分布を把握する目的が強く、出題難易度は標準的で公立高校入試よりもやや難しく作られています。したがって、偏差値や順位は県内での位置を把握するのに有効です。判定は全体の母集団を元に算出されるため、合否の目安として一定以上信頼できる指標になり得ます。
2-3. メリット・注意点
この模試のメリットは、受験者数がある程度大きく母集団が安定している点です。全県的な立ち位置を確認したい家庭には適しています。逆に、問題は比較的標準的なので、難関校対策としては別途難易度の高い模試で鍛える必要があることに注意してください。申し込みは公式HPから個人ですることができます。
3. 志門塾「岐阜模試」の特徴ってなに?
3-1. 出題形式・回数・実施時期
志門塾が実施する「岐阜模試」は、岐阜県入試を徹底的に研究して作られた塾主催の模試です。出題は記述式を含め本番形式を意識しており、解き直し用の実力強化問題も提供されます。実施回数は年間で多めに設定されており、2025年には年7回のスケジュールで運営されています。志門塾の塾生以外の受験生は、指定会場での受験が基本となります。
3-2. 難易度・偏差値・判定制度
岐阜模試は本番よりやや難しめのレベルに設定されることが多く、特に思考力や記述力を問う問題が含まれます。したがって、判定はやや厳しめに出る傾向があり、難関校を志望する生徒にとっては実戦力を磨くうえで有効です。偏差値や合格可能性は内申点とのクロス判定で出され、塾側の分析資料も詳細に提供されます。
3-3. メリット・注意点
メリットは、難問に慣れることができる点と、解き直しや実力強化問題で弱点を徹底的に潰せる点です。特に難関校を目指す生徒には不可欠な訓練になります。一方で会場の都合や、母集団が塾生中心になりやすいことを踏まえ、県全体の位置把握用としては別途母集団の大きい模試と併用することも検討するのが無難です。
4. 受けるべき模試ってなに?模試の選び方とは?
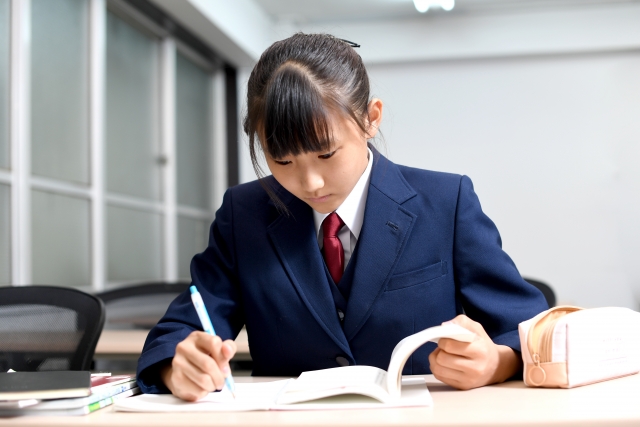
4-1. 公立入試重視派/私立入試重視派での選び方
公立入試を重視する場合は、県全体の目安が分かる岐阜全県模試や岐阜新聞の学力テストを軸にすると良いでしょう。なぜなら、これらは母集団や判定の安定性が高く、志望校の合格可能性を現実的に示してくれるからです。一方で、難関私立やトップレベルの公立高校を目標にするなら、志門塾の岐阜模試のような難度の高い模試で実戦力を磨くことが有効です。目的に合わせて、模試を「位置確認用」と「実力養成用」に分けて選ぶのが得策です。
4-2. タイミングや偏差値・内申点から見た判断基準
夏休み後から本番直前にかけては、模試結果を使って弱点補強を繰り返すことが重要です。偏差値と内申点の両面から合否の見通しを立てるため、クロス判定を提供する模試の利用価値が高まります。特に内申点が低めの生徒は模試での得点改善を優先し、内申が高い生徒は偏差値維持と得点安定を目指すと良いでしょう。複数回受けることで伸びが数字で見えるようになります。
4-3. 模試を有効活用する勉強法のポイント
模試は結果を受け取った後の活用方法によって学力向上の効果が大きく変わります。 まず重要なのは、点数だけでなく設問ごとの正誤や解答の仕方をしっかり振り返ることです。 特に時間配分の失敗やケアレスミスは、次回の模試や本番の入試に直結する改善点になります。 また、模試で判明した苦手単元は、学校の授業や家庭学習で重点的に復習するべきでしょう。 模試後の解説冊子や答案分析を積極的に使えば、効率よく弱点補強ができるはずです。 さらに、模試の偏差値や判定は現状を知る目安であり、一喜一憂するものではありません。 継続して受験しながら「前回よりも伸びた点」「安定して取れる得点帯」を意識すると良いでしょう。 このように模試を学習サイクルに組み込むことで、単なる成績確認ではなく実力を磨く機会になるのです。
5. まとめ
岐阜県の中学3年生向けの模試には、それぞれ異なる目的と強みがあります。岐阜全県模試や岐阜新聞の学力テストは県内での立ち位置を確認するのに適しており、志門塾の岐阜模試は難問で実戦力を鍛えることができる点が強みになります。どの模試を受けるかは志望校・現在の学力・家庭の事情によって変わります。負荷を考慮する必要はありますが、複数の模試を組み合わせて受験するという方法もあります。また、結果を受け取った後は、「問題の解き直し」と「学習計画の際構築」が大切です。最後は日々の学習と家庭のサポートが合格を決める大きな要素になります。お子さんに合った模試選びをして、計画的に受験準備を進めてください。