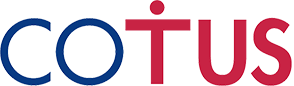岐阜県が作っている中学校のワークって何? -定期テストでは岐阜県のワークに取り組んで高得点を狙おう!-

岐阜県が作っている中学校のワークって何? -定期テストでは岐阜県のワークに取り組んで高得点を狙おう!-
中学生の保護者の方なら「うちの子は学校からどんな教材をもらっているの?」と気になったことがあるでしょう。
実は岐阜県には、県が作成した「岐阜県ワーク」と呼ばれる副教材があり、多くの中学校で活用されています。
このワークは定期テストと深く関わっており、取り組み方次第で大きな得点力アップにつながるのです。
今回は岐阜県ワークの特徴やテストとの関係、活用方法までを詳しくご紹介します。
目次
1. 岐阜県の中学校ワークってなに?どのようなもの?
1-1. 岐阜県ワークの概要
岐阜県ワークとは、岐阜県内の中学校で授業や定期テストに合わせて使われる副教材です。
多くは主要5教科を中心に構成され、授業の進度に沿った問題が掲載されています。
生徒が家庭学習で取り組めるよう設計され、理解度を確認しやすいのが特徴です。
そのため、学校だけでなく家庭学習においても欠かせない存在となっているのです。
1-2. 岐阜県ワークが多くの学校で取り入れられている背景
岐阜県ワークは、学力の底上げを図るために県全体で共通して導入されています。
授業進度とテスト範囲が一致しやすく、指導の効率化につながる点が評価されています。
また、同じ教材を使うことで学校間での学習格差を減らせることも利点です。
このように統一された教材だからこそ、多くの中学校が採用しているのです。
1-3. 学校によって違うワークもある
ただし、すべての中学校が同じように岐阜県ワークを使っているわけではありません。
中には独自に選んだ市販ワークや教科書準拠の副教材を重視している学校もあります。
英語や数学では岐阜県ワークを配布し、国語や社会では別のワークを採用するケースもあるのです。
学校ごとの方針で変わるため、まずは自分の子どもの学校でどんな教材を使っているか確認する必要があります。
そのうえで、配布されたワークをしっかりやり込むことがテスト対策の基本になるでしょう。
「うちの学校は岐阜県ワークじゃなかった」という場合でも心配はいりません。
大切なのは、学校で実際に使っているワークに優先して取り組む姿勢なのです。

2. 岐阜県ワークと定期テストの関係ってなに?関係ある?
2-1. 定期テストはワークから出題されやすい
定期テストの問題は、授業内容をもとに作られるのが基本です。
岐阜県ワークは授業進度に沿って作られているため、出題範囲と重なることが多いです。
そのため、ワークをしっかり解いておけば定期テストでの得点につながります。
「テスト前はワークを完璧に仕上げること」が重要になるのです。
テスト勉強についてはこちらの記事を是非ご覧下さい。
「テスト勉強の仕方、本当にそれで合ってる?」~平均点以上を取るための勉強法~
「テスト勉強の仕方、本当にそれで合ってる?」~400点以上を取るための勉強法~
2-2. ワークをやり込むことが得点アップにつながる
ワークを繰り返し解くことで、知識の定着が加速します。
同じ問題を3回以上解くと、自然とスラスラ解けるようになるのです。
解き直しを重ねることはテスト本番での正答率を大きく上げる方法です。
だからこそ、ただ提出のために解くのではなく「完璧にできるまでやり込む」姿勢が大切なのです。
2-3. 提出課題としてのワークの重要性
岐阜県ワークは、多くの学校で「提出課題」として扱われます。
解答が未完成だったり、丸付けが雑だったりすると評価に響くこともあるのです。
つまり、提出物の観点からもワークはきちんと仕上げておく必要があります。
特に内申点を重視する中学生にとっては、これは見逃せないポイントです。
先生がチェックするのは答案の正確さだけではなく、努力の跡でもあります。
家庭学習の習慣をつけるきっかけとしてもワークは役立ちます。
提出を意識することで「やらざるを得ない」仕組みになっているとも言えるでしょう。
3. 岐阜県ワークを効果的に活用する方法とは?どうすればいい?
3-1. テスト前の勉強計画に組み込む
ワークはテスト勉強の中心に据えるべき教材です。
計画的に進めることで、テスト前に余裕を持って仕上げられます。
逆算してスケジュールを立てることが、得点アップの近道です。
「ワークを徹底的に仕上げてから応用に進む」という流れを意識しましょう。
3-2. わからない問題を放置しない工夫
ワークを解いていてつまずいた問題は、印をつけておくと便利です。
解説を読んでも理解できないときは、学校の先生や塾の先生に質問しましょう。
放置すると次の単元でも同じつまずきが出てしまいます。
質問して解決する習慣が、学力を伸ばす土台になるのです。
3-3. 実際に学校から受け取ったワークを優先して取り組む意義
子どもが手にしているワークこそ、その学校の学習方針を反映しています。
先生がテスト問題を作る際にも、そのワークを参考にすることが多いのです。
したがって「配布されたワークを優先する」ことは最も合理的な勉強法です。
家庭学習の第一歩は「学校ワークのやり込み」であると考えてよいでしょう。
3-4. 学校指定ワークと塾の教材の使い分け
学校のワークだけでは応用力が不足することもあります。
その場合、塾や市販の教材を組み合わせることで発展的な学力を養えます。
例えば、学校ワークで基礎を固め、塾・市販教材で応用問題に挑戦する流れです。
ただし、家庭学習で使う教材が多すぎると混乱するため、優先順位を決めましょう。
「学校ワークを最優先に、その後に塾や市販教材を活用する」のが理想です。
こうした役割分担を意識することで、効率的に学習が進められるのです。
4. まとめ
岐阜県ワークは県全体で導入されている副教材で、定期テスト対策に直結する大切な教材です。
ただし学校によって採用状況は異なるため、まずは自分の子が受け取ったワークを確認することが欠かせません。
実際のテスト問題はワークの内容と重なる部分が多いため、やり込みが得点アップの鍵となります。
また、ワークは提出課題として扱われ、内申点にも影響を与える可能性があります。
活用の仕方としては、テスト前の計画に組み込み、分からない問題は必ず解決する、というのがおすすめです。
さらに、塾や市販の教材を組み合わせることで応用力を磨き、総合的な学力を高められます。
つまり、学校から与えられたワークを軸に勉強を進めることが、最も効果的な学習戦略だといえるでしょう。
お子さんが高得点を狙えるよう、是非今日から岐阜県ワークを意識した学習に取り組んでみましょう!
【無料体験・進路相談はこちら】https://cotus.jp/entry/